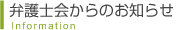- 栃木県弁護士会トップページ >
- 栃木県弁護士会からのお知らせ >
- 地方消費者行政の維持・強化を求める意見書
地方消費者行政の維持・強化を求める意見書
-
第1 意見の趣旨
1 国は、消費生活センターにおける消費生活相談員の人件費に充てることを含む人材確保及び処遇改善に活用できる地方消費者行政に関する交付金を2026(令和8)年度以降も継続または同様の措置を講ずること。
2 全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)の刷新及び相談業務のデジタル化に伴う地方公共団体の設備刷新及び運営の経費を、国において全額負担する措置を講ずること。
3 地方消費者行政の事務のうち消費生活相談体制及び相談情報集約事務、適格消費者団体の活動支援事務など、国と地方公共団体相互の利害に関係する事務であって国全体の水準を確保する必要があるものについては、地方財政法10条の適用によりその全部または相当部分を国が負担することについて検討すること。
4 消費者被害防止に取り組む適格消費者団体の運営及び地域の消費者団体の育成・活動支援・連携のために地方公共団体が行う支援事務に対し、国は財政支援を継続・拡充すること。
第2 意見の理由
1 消費者被害の実情と地方消費者行政
消費者庁の2024(令和6)年版消費者白書によると、2023(令和5)年度の全国の消費生活相談件数は約90.0万件であり、前年よりも約3.3万件増加している。同白書によると、令和5年の消費者被害・トラブル推計額(既支払額(信用供与含む。))は約8.8兆円であり、前年度よりも2兆円以上増加している。
また栃木県が発表した「2023(令和5)年度消費生活相談状況について」によれば、同年度に栃木県内の消費生活相談窓口で受け付けた消費生活相談件数は16,912件であり、前年度、前々年度より増加している。
しかも、悪質な訪問販売被害、詐欺的な定期購入商法被害、SNSのチャットによる詐欺的勧誘被害など、取引のデジタル化に伴う取引形態の複雑多様化、複数事業者の介在と匿名性の悪用などにより、消費者被害を引き起こす悪質業者の手口はますます巧妙化し、高齢者に限らず消費者はますます脆弱な状況に置かれている。
このように、消費者被害は後を絶たず、依然として深刻な状況である。これらの消費者被害を救済し、被害を未然に防止するためには、相談体制の確保をはじめ、地方消費者行政の継続・強化が非常に重要である。そのためには、国が、地方消費者行政にかかる経費を継続的に担っていくことが不可欠である。
しかしながら、地方消費者行政に対する国の財源措置は年々減額されており、さらに以下のとおり、地方消費者行政を継続的に行うのに足るものとなっていない。
2 意見の趣旨 第1項(交付金の継続等)
(1)2014(平成26)年に開始された地方消費者行政推進交付金(なお、2018(平成30)年から地方消費者行政強化交付金に名称及び内容が変更されている。)は、消費生活相談員の人件費にも充てることができ、長い間地方の相談体制を下支えしていた。栃木県においては、消費生活相談員のレベルアップ事業の他、地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業(具体的には、消費者教育・啓発出前講座、各世代向け消費者教育・啓発等。例えば、大学生・高校生に対する消費者教育講座「とちぎ消費者カレッジ」等)にも充てられ、地域における消費者教育をも支えてきた。
しかし、2024(令和6)年度末及び2025(令和7)年度末に多くの自治体で同交付金の活用期限が終了することになる。そうすると、多くの地方公共団体の財政状況が厳しい状況にある中、消費生活相談員の減員や相談窓口開設日の削減、消費者教育事業の削減等に追い込まれる恐れが大きい。
(2)消費生活相談員は、消費者法制度及び消費者問題の専門的知見を必要とする資格保有者であり、かつ消費者及び事業者の双方から事情聴取して適正な解決に向け調整する能力の継続的な研鑽と経験の蓄積が不可欠とされる高度の専門職である。
ところが、現状は、定期昇給制度のない会計年度任用職員制度が適用されている結果、高度の専門性に見合う処遇となっていない。近年は、全国的に消費生活相談員の担い手の確保が困難な状態や欠員が生じる深刻な事態となっている。
そこで、消費生活相談員の高度の専門性に見合う処遇の改善を図るため、国は人件費に充てられる地方消費者行政強化交付金による強力な財政支援を継続または同等の措置を講ずることが喫緊の課題である。
また、消費生活相談員の雇用に、専門性が高い業種に見合う処遇が得られず、任期制のため安定雇用が確保されない会計年度任用職員制度が用いられていることが、消費生活相談員の担い手不足の原因のひとつであるといえる。国が予算措置を講じて専門職任用制度の創設・整備をすることにより、消費生活相談員の担い手不足の解消を図るべきである。
3 意見の趣旨 第2項(PIO-NETの刷新のための費用負担)
PIO-NETは、全国の消費生活相談情報を集約し、国や地方公共団体の消費者啓発情報として活用するほか、国や都道府県の事業者規制の端緒情報として活用し、国は消費者法制度見直しの情報として活用するなど、我が国の消費者行政全体の情報基盤である。
そのPIO-NETの刷新時期が2026(令和8)年に迫っており、国は新たなPIO-NETシステムを地方公共団体共通のLGWANシステムの中に位置づけ、端末機の配備等につき何らかの財政支援措置を講ずる方針を示している。しかし、新システムの運用において、各地方公共団体に新たな財政負担が生じることが危惧されている。
PIO-NETは、消費生活相談情報を国と地方公共団体全体で共有するための不可欠のシステムであり、設備導入の形式が変更されるとしても、その経費はこれまでどおり国において負担すべきものである。
4 意見の趣旨 第3項(国と地方の費用分担の在り方)
そもそも地方消費者行政は、地域住民に対するサービス提供であり自治事務であると位置づけられてきた。
しかし、消費生活相談業務は、消費者安全法8条により地方公共団体が実施しなければならない事務であり、地域の相談者に対するトラブル解決に向けた助言にとどまらず、特定商取引法など消費者関連法の違反行為の有無を聴取し、その相談情報をPIO-NETを通じて国と地方公共団体全体が共有するなど、全国の消費者行政の基盤である。
また、適格消費者団体の差止請求業務は、法令違反行為の差止請求活動により消費者被害の防止及び国全体の市場の適正化の役割を果たすものである。
このように地方消費者行政の事務の中には、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務であって、国全体の消費者施策を円滑に運営するためには全国の水準を維持・向上することが必要とされる事務が含まれており、国がその全部または相当部分を将来に向けて負担すべきである。そこで、安定的な地方消費者行政を運営するためにも、地方財政法10条に「消費者行政に関する事項」を新設することを含め、今後更なる検討をすることが求められる。
5 意見の趣旨 第4項(消費者団体に対する支援)
適格消費者団体の活動は、制度スタートから約18年間に、26団体が認定を受け、差止請求訴訟の提起や裁判外の申入れ活動により、消費者被害の防止と市場の適正化に資する極めて公益性の高い活動を担っている。
しかし、こうした差止請求活動の多くの部分が専門家の無償ボランティアによって支えられている実態がある。行政庁の役割の代替機能を果たしているともいえる適格消費者団体の活動が、人的基盤及び財政基盤において持続可能となるためには、国や地方公共団体による公的財政支援の充実が不可欠である。
また、地域の消費者団体は、消費者被害防止のための見守りネットワークの担い手の役割、一般消費者に向けた注意喚起や消費者の意見の収集・表明の役割、適格消費者団体の運営の担い手の役割など、消費者政策を円滑に運営するうえで不可欠の幅広い役割(消費者基本法8条)が期待されている。消費者基本法26条は、「国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。」と定めている。
しかし、一般消費者団体の育成・支援に関する国の施策や財政支援措置が大幅に縮小・後退し、地域の多くの消費者団体が構成員の高齢化、活動の衰退・消滅など、深刻な事態となっている。地方消費者行政が真に機能するためには、地方公共団体と連携して消費者被害防止の主体的な活動を展開する消費者・消費者団体を育成・支援することが不可欠である。
6 結語
よって、財政力の脆弱な地方公共団体を含め国全体の地方消費者行政の水準を維持・強化するため、意見の趣旨に記載したとおり、国の強力な支援措置の継続または同様の措置を求める。
以上
2025(令和7)年4月7日
栃木県弁護士会会長 杉田 明子